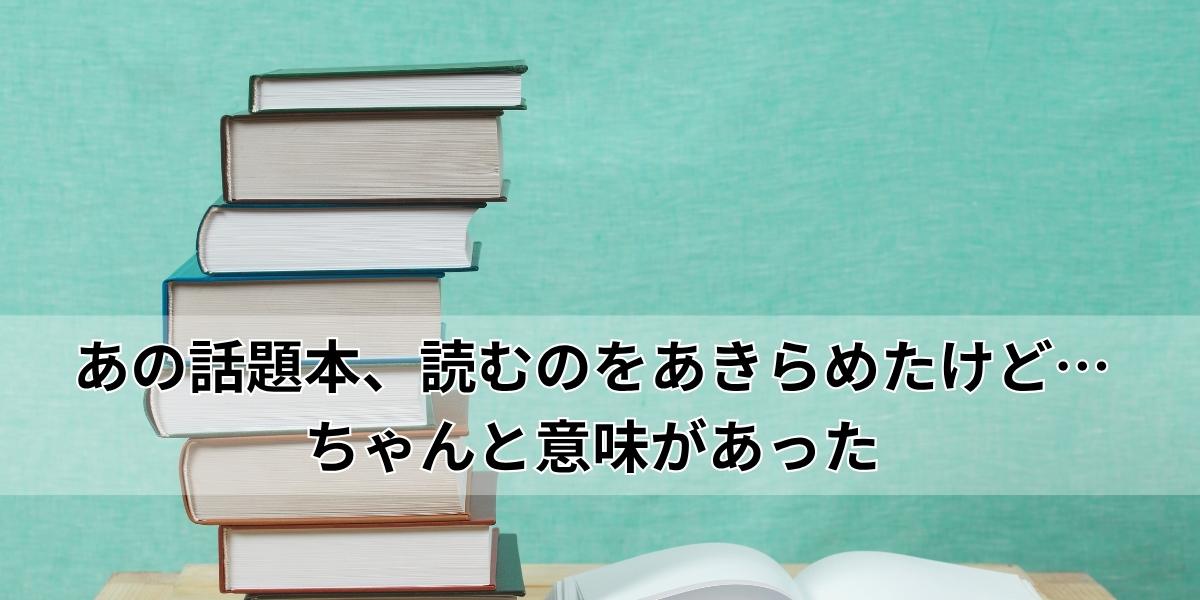『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』──私が“挫折”した一冊
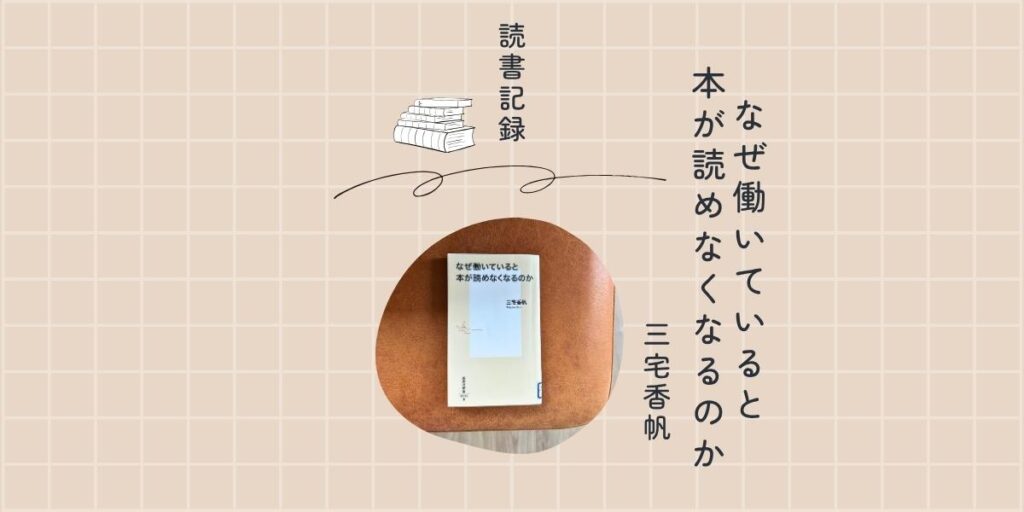
最近読んだ一冊に、ふっと気持ちがほどけるような瞬間がありました。
忙しない日々の中で、自分の心に少しだけ時間をあげるように読む本。
今日は、そんな本の感想をゆるりと綴ってみます。
本好きでも「読めない本」はある
「これは絶対に読みたい」と思って図書館で予約。
何ヶ月も待ってようやく届いたその本。
三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』

なぜ働いていると本が読めなくなるのか (集英社新書) [ 三宅 香帆 ]
タイトルからして、まさに自分ごと。
働きながら本を読む時間をどう確保するか、悩んでいたところだった。
いざ読み始めた夜――
まさかの「秒で眠くなる」という事態に(笑)

「情報が多い本」は、私の鬼門だった
漢字びっしり、説明多め、資料や引用も豊富。
丁寧で誠実で、真面目な本だとわかるのに、どうしても頭に入ってこない。
一方で、「さくらももこ」や「フリッパーズギター」など、
好きなワードが出てくるパートだけは、すらすら読める。
要するに、相性の問題だった。
挫折本に自信をなくした過去
ふと、かつて読み切れなかった本の記憶がよみがえる。
『アルジャーノンに花束を』も、『ノルウェイの森』も、結局最後まで読めなかった。
あのときは「自分はダメなんだ」と落ち込んだ。
本好きなのに、話題の名作が読めない自分が情けなく思えた。
でも今は、「読めない自分」も含めて受け入れられるようになった。
人には“合う時期”と“合わない時期”があって、読むことに正解なんてない。
逆に、一気に読めた本たち📌 書籍リンク一覧
文章のテンポ、構成、キャラクター、全部が自分にフィットしていた。
「読める」ときの快感も知っているからこそ、
「読めない」ときの自分を責めなくてよくなった。


読書って、自分を知る時間かもしれない
この本で印象的だった一文。
「文脈を知ることが大事」
まさにその通りだと思う。
たとえ読みづらくても、知らない視点に触れることは価値がある。
無理に好きになる必要はないけれど、
「合わなかったけど、ちょっとだけ理解した」という感覚は、たしかに残った。
図書館という、最高の“積読”システム

最近、紙の本を買いすぎて置き場に困るようになってきた。
そんなときこそ図書館。
読みたい本をどんどん予約して、少しずつ出会っていく。
返却期限があるおかげで、“読書の背中押し”にもなる。
たとえ読めなかった本があっても、それも立派な読書体験。
きっと、また別の一冊が、自分の気持ちを代弁してくれる日がくる。
まとめ
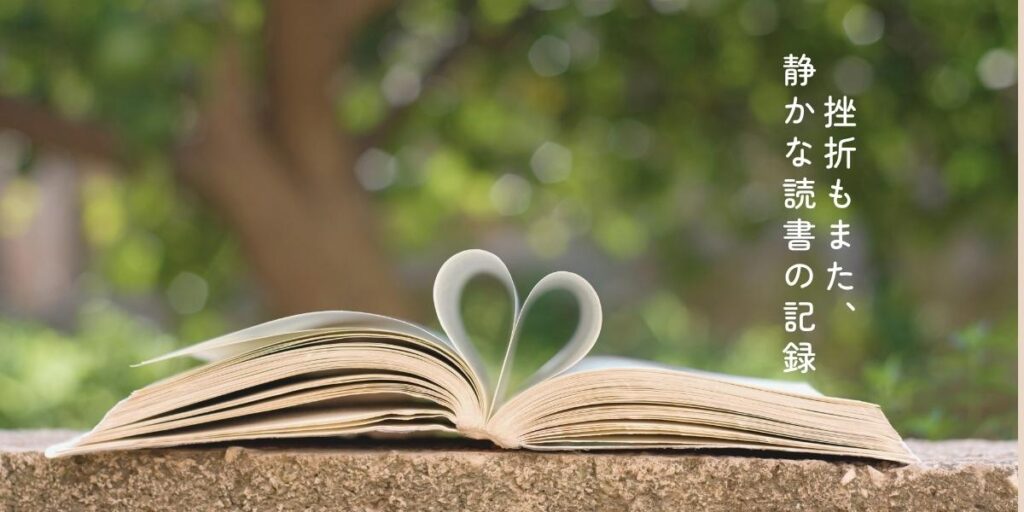
- 読めなかった本にも、ちゃんと意味がある
- 読書は「合う」「合わない」でよい
- 本との出会いは、自分を知る時間でもある
- 図書館は読書の味方
読めなかったけど、ちゃんと最後まで目を通しました。
挫折もまた、静かな読書の記録です。
何かオススメの書籍などありましたらぜひ教えてください!