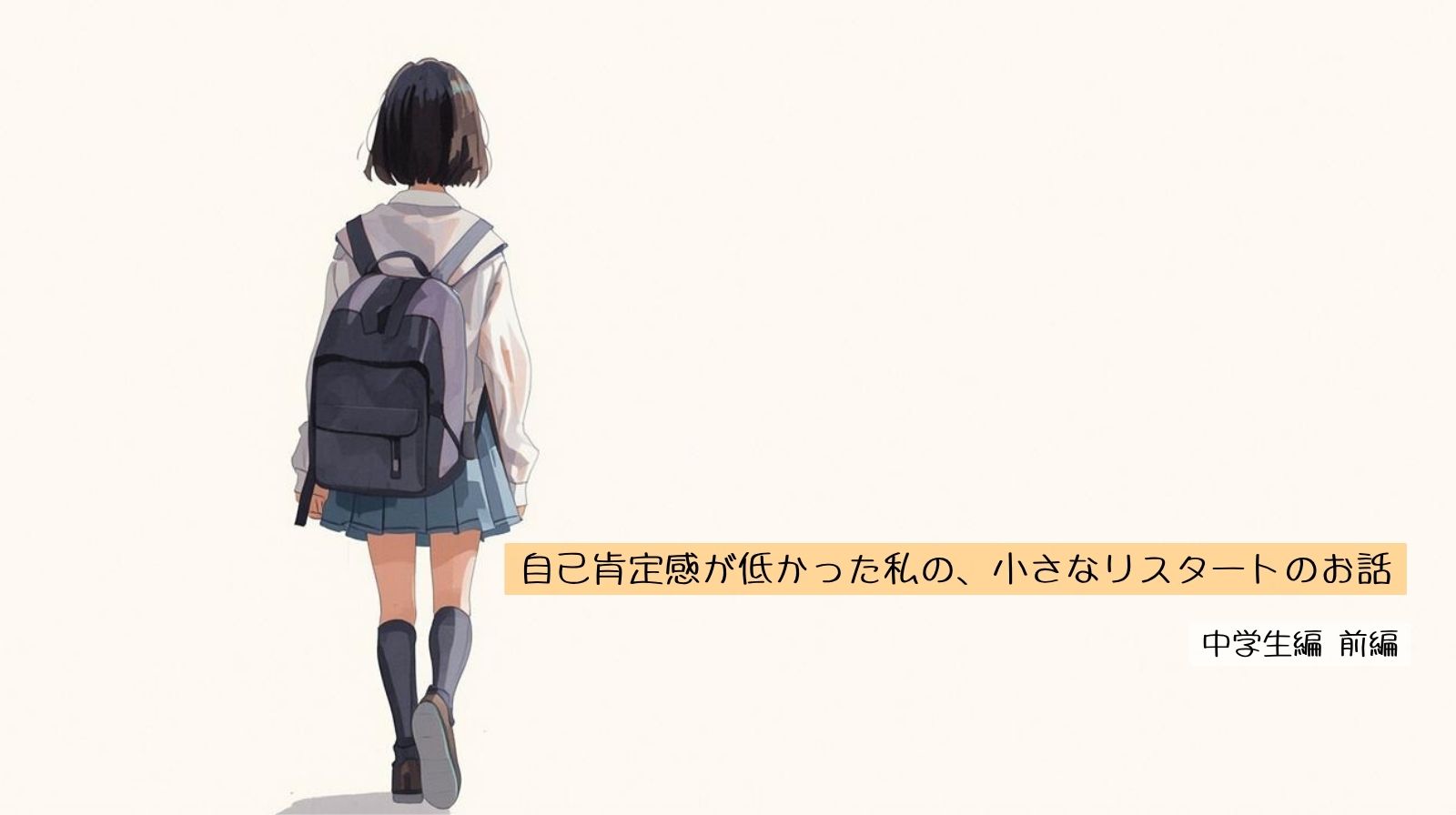小学生から中学生へ 〜吹奏楽部で過ごした“もくもく学生生活”〜
中学生になると、部活動や人間関係の中で「自分って何者なんだろう」と悩む子も多いですよね。
私もまさにその一人で、思春期の不安や劣等感を抱えながら吹奏楽部に入部しました。
小学生の頃から続いていた“自己肯定感の低さ”は、中学に入ってもすぐには変わらず、
「うまくやらなきゃ」「間違えたら怒られる」と周りを気にしてばかりの日々。
そんな私が、吹奏楽部という小さな世界で少しずつ“自分を受け入れる”ようになった、
その始まりの物語です。
小学生から中学生へ

小学生時代を振り返る中で、「自己肯定感が低かったな」と強く感じました。
子ども時代の思い出は、楽しかったよりも「比べられることの苦しさ」の方が大きかったのです。
そして迎えた中学生時代。
いきなり性格が変わるわけもなく、私の“もくもく学生生活パート2”が始まりました。
通学は自転車で片道30分以上。
小さな小学校から、学年9クラスもある大きな公立中学に進学することになり、不安と緊張を抱えてのスタートでした。

9クラスもあったの?

今だと考えられないよね〜
部活動の選択と「最大の誤算」

中学に入ると、強制的に部活動へ参加する流れがありました。
運動が大の苦手な私は、迷わず文化部を探しました。
ただ、その中で特別にやりたいものもなく…結局、小学校の同級生が入った吹奏楽部へ。
これが今思えば「最大の選択ミス」でした。
女子ばかりの吹奏楽部。最初に行う楽器選びで、私は木管楽器のフルート・クラリネット・サックスすべて音が出ず、
仕方なく音が出たトランペットに。しかも担当は“3rd”というサブのさらにサブ。
華やかさもなく、譜面もほぼ読めず…ただひたすら「間違いがバレませんように」と願う日々でした。

俺は運動部

しらんがな〜

恐怖の顧問教師

本当の問題は、吹奏楽部の顧問でした。
当時40代くらいの男性教師。ベビースモーカーで喫煙室常連。
気に入らないことがあると、大声で怒鳴り、時には机や椅子を投げ飛ばす…。
今なら完全にパワハラ・モラハラ案件です。
当時は「不良文化」が全盛期で、先生たちも圧の強い人が多かった時代でしたが、
それにしても異常でした。
そんな恐怖の顧問のもと、吹奏楽部は県大会まで進むという“実績”を残してしまい、私にとっては地獄の日々。
夏休みも冬休みも、毎日お弁当を持って自転車で部活へ。辞めるという選択肢はありませんでした。
結果、部活動を通して「楽しかった」という記憶はゼロ。
ただ「どうにかやり過ごす」ための3年間でした。

ネタ?と言って・・・

・・・事実です

部活動から見えた“もしもの選択肢”

大人になった今振り返ると、もし自己肯定感がしっかりしていて、自分の意志をはっきり持てていたら――
きっと写真部やパソコン部のような、自分に合った選択肢を選んでいたかもしれません。
でも当時は家にカメラもパソコンもなく、親も費用を納得しなかったでしょう。
結局「仕方なくの選択」で、地獄のような吹奏楽部生活を過ごしたのです。
子どもたちの部活と比べてみて
私には娘と息子がいます。
長女は運動神経抜群で、中学はテニス部、高校は陸上部。
大会で記録を残すこともありました。
一方の長男は「人と競わなくていいから」という理由で陸上部の砲丸投げを選び、その後は卓球部へ。
しかし部員が次々やめてしまい、結局退部。
親になって改めて思うのは、「部活動の経験って人によって全然違う」ということです。
私にとっては“苦痛の象徴”だった部活動も、子どもたちには「自分の居場所」や「挑戦の場」になっていました。

俺も運動神経バツグンだったで〜!

美術センスとかは皆無だよね〜
当時と今の人気部活ランキング

| 時代 | 男子の人気部活動 | 女子の人気部活動 | 特徴・背景 |
|---|---|---|---|
| 1980年代(傾向) | 野球・サッカー・ソフトテニス・バスケットボール | バレーボール・ソフトテニス・吹奏楽 | 野球・サッカーが「青春の象徴」。漫画やテレビの影響も大きい。文化系は吹奏楽が根強い人気。 |
| 現在(令和6年度調査) | 1位バスケ、2位サッカー、3位軟式野球、4位卓球、5位ソフトテニス | 1位バレー、2位ソフトテニス、3位バスケ、4位卓球、5位バドミントン・吹奏楽 | 野球は相対的に低下。バスケ・卓球・バドミントンが台頭。吹奏楽など文化部の人気が上昇。少子化や価値観の多様化が背景。 |
ちなみに調べてみると、時代を超えて吹奏楽部は上位に残っているんですね。
ただ私にとっては、キラキラ輝く青春ではなく「日々を耐え抜く場」でした。
吹奏楽部で過ごした自己肯定感と静かな成長の記録
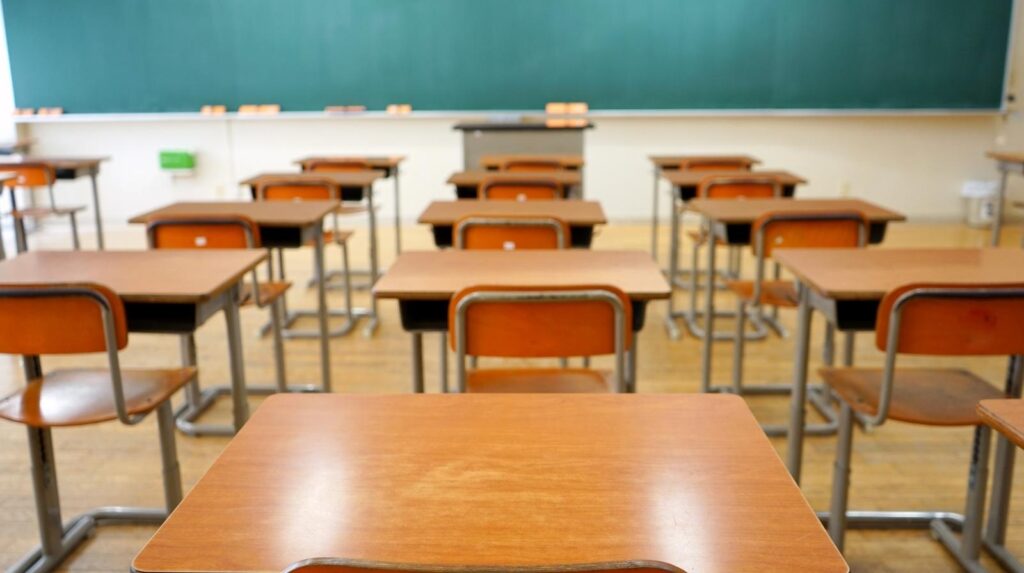
小学生時代から続く“比べられる苦しさ”と“自己肯定感の低さ”。
それを抱えたまま始まった中学生活は、吹奏楽部という舞台でさらに「やり過ごす日々」へと続いていきました。
でもこの経験があったからこそ、今の私は「子どもには無理に合わない場を押しつけない」ことの大切さを強く感じています。
部活動という“小さな社会”の中で、私は自分の心を守る術を少しずつ学んでいたのかもしれません。
次回の「中学生編・後編」では、吹奏楽部での苦しい日々が、どのようにして私の“心の芯”を育てていったのかを綴ります。
逃げ場のない環境のなかで、私はどうやって自分を守り、どうやって折れずにいたのか。
あの頃の私を思い出すたび、今の自分の中に静かに残っている“強さの種”を感じます。
もし、過去の自分に会えるなら「ちゃんと頑張ってたよ」と伝えたい。
どうぞお付き合いください。

なんか、ふびんや

書いててそう思うわ〜
心を軽くしてくれた本との出会いもご紹介します。
精神科医・藤野智哉先生

精神科医が教える 子どもの折れない心の育て方 [ 藤野 智哉 ]

「自分に生まれてよかった」と思えるようになる本 心が軽くなる26のルール [ 藤野 智哉 ]

人間関係に「線を引く」レッスン 人生がラクになる「バウンダリー」の考え方 [ 藤野智哉 ]